大相撲における「巴戦」とは、本割が終了した千秋楽の時点で、優勝を争う力士が複数人同成績で並んだ場合に、優勝者を決定するための特別な戦いの方式を指します。特に、力士が3人以上いる場合に行われる優勝決定戦の一種です。若年層の相撲ファンにはあまり馴染みがないかもしれませんが、幕内では過去に数回しか行われておらず、最近では20年以上行われていない時期もありました。大相撲の巴戦とはいったい何なのでしょうか、特別なルールがあるのでしょうか、そして不公平と言われる理由についても深く考察していきます。

Contents
巴戦の基本ルール:どんな時に行われる?
巴戦の基本:どんな時に行われる?
巴戦は、千秋楽の本割終了時点で、優勝候補の力士が3人以上、同じ成績(相星)で並んだ場合に実施されます。つまり、複数の力士が同点で優勝の可能性を残している時に、誰が優勝するのかを決めるために行われる、いわば「決勝戦」のような位置づけです。
巴戦に参加する力士の人数と条件
巴戦に参加する力士の人数は、主に3人の場合が多いです。千秋楽結びの一番まで終了した時点で、最優秀成績者が同点三者出た場合に「三つ巴戦」という方式で優勝者を決定します。また、同点力士が5人や6人となった場合も、予選を行って3人に絞り、最終的に巴戦を行うことがあります。一方で、4人、7人、8人の場合は巴戦ではなく、単純なトーナメント形式で決定戦を行います。9人から12人の場合は、原則として5人または6人に絞り、さらに3人に絞って巴戦となることもありますが、9人の場合は過去に例外的にまず9人のうち2人を対戦させてその敗者を脱落させ、8人にした上でのトーナメントとなった例も存在します。
巴戦の勝敗ルール:どうなれば優勝が決まる?
巴戦の勝敗ルールは、**「連続して2勝した力士が優勝となる」**というものです。
具体的には、まず優勝決定戦に出場する3人の力士が土俵下でくじ引きをします。くじには「東」「西」「〇(丸)」と書かれた紙があります。「〇」を引いた力士は最初の取組が休みとなり、残りの2人(「東」と「西」を引いた力士)が東西に分かれてまず対戦します。
最初の取組の勝者は、続けて休んでいた「〇」を引いた力士と対戦します。ここで勝った場合、その力士が2連勝となり優勝が決まります。もし負けてしまった場合は、その力士は土俵を降り、初戦で負けた力士が土俵に上がります。その後は、誰か一人が2連勝するまで取組が続けられます。
「東」または「西」を引いた力士は、最初の対戦で負けても、一旦控えとなって次に「〇」を引いた力士が勝てば再び対戦できるため、優勝の可能性が残ります。しかし、「〇」を引いた力士は、自分にとっての最初の対戦で負ければ、その時点で相手力士の優勝が決まってしまうため(相手はすでに先勝しているため2連勝となる)、優勝の可能性がなくなってしまいます。
巴戦の途中で負けた後、再び登場する力士は、前に対戦した時とは東西が逆側からの登場となります。これは、巴戦では誰かが2連勝すればその力士を優勝として終了するため、途中で負けた力士が再び登場するには、前に勝った力士が負けるという条件が必要だからです。
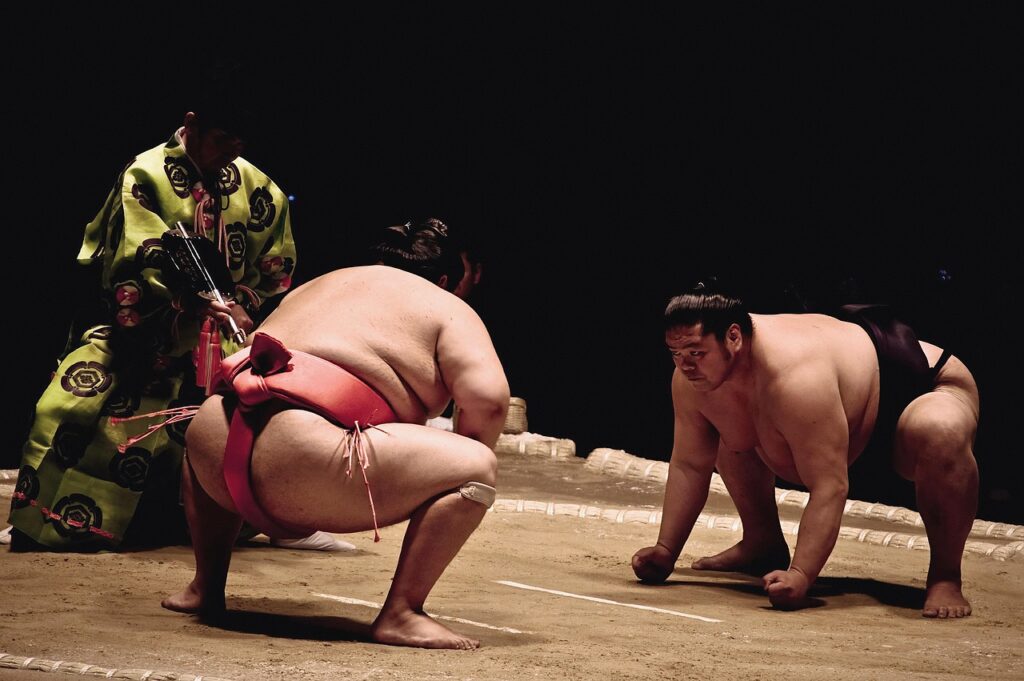
大相撲巴戦の歴史と過去の事例
過去の巴戦:印象的な一番と結果
幕内において巴戦が行われた例は少ないものの、これまでに3人による決定戦で7回、5人による決定戦の決勝戦として1回、巴戦が行われています。
特に印象的な事例として、1990年(平成2年)3月場所の巴戦が挙げられます。この時は、東大関の小錦さん、西横綱の北勝海さん、東関脇の霧島さんの3人による決定戦で、史上最多の4番を要しました。初戦で小錦さんに敗れた北勝海さんが、その後霧島さん、小錦さんに連勝して優勝するという、「逆転の巴戦」として大いに盛り上がりました。
また、史上初の巴戦は1956年(昭和31年)3月場所に行われ、東大関の若ノ花さん(のちの初代若乃花さん)、東前頭15の若羽黒さん、東関脇の朝汐さん(のちの3代朝潮さん)の3人によるもので、結果的に朝汐さんが優勝しました。
2022年(令和4年)11月場所では、東前頭筆頭の髙安さん、西前頭9の阿炎さん、東大関の貴景勝さんの3人による巴戦が行われ、阿炎さんが初優勝を飾りました。
巴戦の出場力士が3人・4人・5人の場合
巴戦は主に3人の力士で行われます。この場合、前述の通りくじ引きで休みの力士を決め、2連勝した力士が優勝となります。
同点力士が4人の場合は、巴戦ではなくトーナメント方式で決定戦が行われます。幕内で4人による優勝決定戦が行われたのは、1947年と1997年の2回です。例えば、1947年6月場所では、9勝1敗で羽黒山さん、前田山さん、東冨士さん、力道山さんの4人が並び、横綱羽黒山さんが優勝しました。また、1997年3月場所では、12勝3敗で貴乃花さん、曙さん、武蔵丸さん、魁皇さんの4人が並び、横綱貴乃花さんが優勝を飾っています。
同点力士が5人、あるいは6人の場合は、まず予選を行って3人に絞り、その後巴戦が行われます。過去には、1996年(平成8年)11月場所で、曙さん、若乃花さん、武蔵丸さん、貴ノ浪さん、魁皇さんの5人が11勝4敗で並び、5人による優勝決定巴戦が行われました。この時は、1回戦で曙さんがシードとなり、魁皇さんと貴ノ浪さん、武蔵丸さんと若乃花さんが対戦し、勝ち上がった貴ノ浪さんと武蔵丸さんが、シードだった曙さんと共に巴戦を行い、最終的に武蔵丸さんが優勝しました。
巴戦に関する様々な記録:最長記録や優勝決定戦の頻度
巴戦が2連勝する力士が出るまで続けられる性質上、取組が長引くこともあります。幕内で行われた巴戦の中で、最も多くの取組を要したのは、前述の1990年(平成2年)3月場所の4番です。
幕内での巴戦は、横綱や大関といった強い力士がいる中で行われることが少ないため、実施例は多くありません。十両や、7番しかない幕下以下ではしばしば行われています。例えば、2020年(令和2年)7月場所では、十両で5敗力士6人による優勝決定戦が行われ、明生さんが優勝しました。また、2001年(平成13年)7月場所の十両では8人での優勝決定戦が行われており、これは優勝決定戦を行った中で史上最多の人数です。
幕内で巴戦が珍しい理由としては、幕内では強い上位力士と対戦することが多く、千秋楽まで横綱や大関と相星で優勝決定戦まで進むことが簡単ではないことが挙げられます。また、幕下以下は1場所に7日しか相撲を取らないため、必然的に相星となることが多くなります。
大相撲巴戦にまつわる疑問と深掘り
なぜ「巴」と呼ぶのか?語源と意味
「巴戦」という名称の語源については、提供されたデータベースには直接的な記述はありませんでした。しかし、「三つ巴」という言葉が相撲の優勝決定戦を指す際に使われることから、三者が渦を巻くように絡み合って戦う様子が、家紋などに見られる「巴紋」の形に似ていることからそう呼ばれるようになったと考えられます。

巴戦は不公平?公平性に関する議論
巴戦の公平性については、確かに疑問を抱く人もいるかもしれません。特に、「〇」を引いた力士が若干不利になるという点が指摘されることがあります。「東」または「西」を引いた力士は、最初の対戦で負けても、次に「〇」を引いた力士が勝てば再度対戦して優勝するチャンスが残される一方で、「〇」を引いた力士は自分にとっての最初の対戦で負ければ、即座に優勝の可能性がなくなってしまうためです。
しかし、巴戦の目的は、直接対決が不可能な状況でも勝敗を決めるための一つの方法です。このシステムが完全に公平かどうかは、各力士が同等に戦う機会が与えられているかどうかによって評価されます。提供されたデータベースでは、この点について「実力が互角でそれぞれの戦いの勝率が1/2同士であることを仮定してそれぞれの力士の優勝確率を計算すると、〇を引いた力士の優勝確率は4/14(勝率約0.286)であり他の2人は5/14(勝率約0.357)であって、〇を引いた力士が不利となる」と述べられています。ただし、幕内で過去7回行われた巴戦で3回〇を引いた力士が優勝しており、これらはいずれも2連勝目が前頭で、「実力が互角でそれぞれの戦いの勝率が1/2同士である」という仮定が成り立たない例であったことも付け加えられています。
巴戦のデメリットとして、BとCの力士が直接戦わないため、BとCの実力が同じでも決定的な戦いが行われない点が挙げられることもあります。視聴者の中には、複数の力士が同じ成績で並んだ場合に、全員が戦うことなく決まることに不満を感じる人もいるかもしれません。私の経験上、この「〇」を引いた力士の不利は、特に精神面への影響が大きいと考えます。初戦を休むことで、他の2人の力士の取り組みを土俵下で待つ間、緊張感が高まり、心理的なプレッシャーが増す可能性があります。また、もし最初の取り組みの勝者がそのまま自分に勝った場合、一度も相撲を取らずに優勝を逃すという状況は、力士にとって非常に受け入れがたいものになるでしょう。
巴戦と確率論:勝敗を左右する要素とは?
巴戦における勝敗を左右する要素には、くじ運と力士の実力、そして精神的な側面が考えられます。
くじ運に関しては、前述の通り「〇」を引いた力士が不利となるという確率論的な見解があります。これは、「東」または「西」を引いた力士が最初の対戦で負けても、相手が勝てば再度対戦のチャンスがあるのに対し、「〇」を引いた力士は最初の自身の取組で負けると優勝の可能性がなくなってしまうためです。
力士の実力ももちろん重要な要素です。実力が互角でない場合、確率論が示す通りの結果にならないこともあります。データベースの記述にもあるように、過去の幕内巴戦で「〇」を引いた力士が優勝した例は、実力が互角でない状況でのものでした。
また、巴戦は短期間に連続して相撲を取るため、体力的な消耗も大きく、精神的な集中力も問われます。1番の相撲を取るのには相当の体力を使うため、長引かせずに一気に決めたいという心理が働くこともあります。実際に、初戦勝利の力士がそのまま連勝したケースや、初戦休みだった力士が迎え撃って連勝したケースが見られます。1990年春場所の巴戦のように、初戦に敗れた北勝海さんが逆転優勝を飾った例もあり、体力や精神力が勝敗に大きく影響すると言えるでしょう。
巴戦が起きる条件として、実力が近い力士が多い場合に発生する可能性が高くなるとも考えられています。絶対王者が怪我で休場していたり、次の実力者が上がって来るまでの狭間の時期に起きやすい印象があるという見解もあります。これは、実力が拮抗している力士が多い場所ほど、千秋楽まで優勝争いがもつれる可能性が高まるためです。
大相撲の巴戦の基本ルールのまとめ
- 巴戦は千秋楽に同点複数力士がいる場合の優勝決定戦だ。
- 主に3人の力士で行われる特別な方式である。
- くじ引きで休む力士を決め、2連勝で優勝となる。
- 「〇」を引いた力士は初戦で敗れると優勝を逃す。
- 過去には5人や6人の巴戦も実施された。
- 4人、7人、8人の場合はトーナメント方式である。
- 幕内での巴戦開催は非常に稀である。
- 1990年3月場所の巴戦は4番を要した。
- 「〇」を引いた力士は心理的に不利となる。
- 実力拮抗力士が多いと巴戦が起きやすい。

コメント