 うさぎくん
うさぎくん育てている多肉植物に白いカビがついているんだ、どうしよう。



多肉植物についた白いものはカビとも限らないよ。この記事で詳しく説明するよ。
多肉植物を育てていると、葉や茎、鉢の表面などに白いふわふわや粉のようなものが現れることがあります。この白い正体が「白カビ」なのか、それとも無害なものなのか判断に迷われる方も多いのではないでしょうか。特に湿度の高い環境や風通しの悪い場所では、白カビが発生しやすくなり、放置すると植物の健康を損ねてしまうこともあります。
本記事では、「多肉植物 白いカビ」に関する原因や見分け方、そしてカビが生えてしまった場合の具体的な対処法について詳しくご紹介します。アルコールを使った除去方法や、実際に使える殺菌剤の選び方も解説。さらに、再発を防ぐための環境づくりや育て方のポイントにも触れています。多肉植物のカビ対策に悩む方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 白いカビの正体や見分け方がわかる
- 白いカビが発生する原因が理解できる
- 白いカビの効果的な除去・対処法が学べる
- 白いカビの予防や再発防止策が把握できる
Contents
多肉植物の白いカビの原因と見分け方


多肉植物の白いふわふわの正体とは?
多肉植物の葉や茎に見られる白いふわふわした物体は、主に「カビ」「カイガラムシ」「ブルーム」のいずれかです。中でもカビは湿度の高い環境で繁殖しやすく、風通しの悪い場所や水やりの頻度が多すぎると発生しやすくなります。ただし、すべてが害ではありません。例えばブルームは、エケベリア属などの多肉植物が乾燥や日差しから身を守るために自ら分泌する天然の粉です。一方、カイガラムシは害虫で、樹液を吸って植物を弱らせる原因になります。これらは見た目が似ていて紛らわしいですが、ブルームは粉状で均一に広がり、カビや虫は局所的に発生します。見分け方に注意し、正しい判断で対応しましょう。
白い粒はカビなのか?
白い粒が見える場合、それがカビであるかどうかは粒の形や発生場所によって判断できます。一般的に2mm程度の白い粒で丸く、葉や茎に点在するものは「カイガラムシ」の可能性が高いです。これは害虫であり、放置すると植物全体に被害が広がります。一方で、土や茎の根元に白くて綿のような質感が見られる場合は、カビである可能性が高まります。いずれにしても、早期発見と対応が重要です。柔らかい歯ブラシなどで取り除ける場合は掃除し、それでも改善しない場合は薬剤による駆除を検討してください。どちらにしても放置は禁物であり、症状が進行すると植物の生育に悪影響を及ぼすおそれがあります。
多肉植物の白い粉:病気との関係
多肉植物の葉に見られる白い粉は、病気とは限りません。最もよくあるのが「ブルーム」と呼ばれる天然のワックス成分で、これは植物が自らを紫外線や乾燥から守るために分泌するものです。ブルームは病気ではないため、無理に取り除く必要はありません。対して「うどんこ病」という白カビの一種も白い粉のように見えるため、見た目だけでは判断が難しいことがあります。見分けるポイントは、粉が広範囲に広がっていたり、葉に変色や縮れが見られるかどうかです。そうした変化があれば、病気を疑って対処を検討すべきです。誤ってブルームを病気と勘違いしないよう、植物の種類や状態を確認することが大切です。


白カビはやばい?健康への影響
白カビは見た目には小さな異変でも、放置すると人体や植物に悪影響を与える可能性があります。室内で多肉植物を育てている場合、空気中にカビの胞子が飛び散ることもあり、アレルギー体質の方や呼吸器系に不安のある人には注意が必要です。特に免疫力の低い高齢者や子どもがいる家庭では、こまめにカビの有無をチェックしましょう。また、白カビは植物にも悪影響を及ぼし、根腐れや成長不良の原因になることがあります。一見無害に見えても、広がる前に対処することが大切です。風通しの良い場所で育てることや、湿度管理を徹底することで予防につながります。
植木鉢に白いカビが生えたらどうすればいい?
植木鉢の表面に白いカビが生えてしまったら、まずは慌てず、風通しの良い場所に鉢を移動させましょう。次に、表面の土をスプーンなどで丁寧にすくい取ります。このとき、土が乾いているかを確認してください。湿ったままでは再発する可能性が高くなります。取り除いた後は、新しい清潔な土を追加し、以降の水やりは控えめにします。また、鉢自体が通気性の悪い素材である場合は、素焼き鉢などに替えるのもひとつの方法です。さらに、鉢皿に水が溜まったままにしないなど、日常的な管理の見直しが重要です。カビは「湿気・温度・栄養」の三要素が揃うことで繁殖するため、この3つを抑えることがカビ予防の基本です。
多肉植物のカビ 葉に現れる初期症状
多肉植物の葉にカビが発生した場合、初期段階では白や灰色の粉状のものがうっすらと広がって見えることが多いです。特に葉の根元や影になる部分にカビが出やすく、油断していると一気に広がります。また、葉の表面がベタついていたり、黒ずみが出てきたら注意が必要です。カビが原因で葉が変色したり、柔らかくなってしまうこともあります。このような兆候を見逃すと、茎や根まで影響が及ぶこともあるため、早期発見がとても重要です。葉に異変を感じたときは、すぐに拭き取ったり、該当部分を取り除くなどの対処を行いましょう。また、カビが再発しないよう、風通しをよくして乾燥気味に育てることも大切です。
多肉植物に白いカビが生えた時の対処と予防
白カビが生えてしまったらどうすればいい?
白カビを見つけたときは、まず多肉植物と周囲の環境を見直しましょう。風通しが悪かったり、水を与えすぎている場合には、環境がカビの繁殖を助けている可能性があります。対処の第一歩は、カビが付いた部分を優しく取り除くことです。ティッシュや歯ブラシで軽くこすり、場合によってはアルコールスプレーを使って消毒します。それでも落ちない場合は、植え替えが必要になるかもしれません。カビの発生が土の内部まで及んでいる可能性があるからです。また、使用する器具はすべて清潔に保ち、作業後も手洗いを忘れないようにしましょう。再発防止のために、育てる環境も改善することが求められます。


カビが生えた時の対処法は?
カビが発生した場合の対応は、症状の進行具合によって異なります。表面だけであれば、該当部分を取り除いて乾いた土を追加する程度で済みますが、根のまわりまで広がっている場合には植え替えが必要です。このとき、新しい鉢と新しい土を用意し、植物を一度取り出して根をよく観察します。カビがついている部分は取り除き、2〜3日ほど陰干ししてから再び植えます。作業中は風通しの良い場所で行い、作業後は清潔な状態に保ちましょう。重要なのは、すぐに対応することです。放置すると植物全体に被害が広がり、最悪の場合枯れてしまうこともあります。
カビ対処方法の具体的手順
カビを効果的に対処するためには、段階的に手順を踏むことが大切です。まず、カビの種類と場所を確認します。葉や茎に付着している場合は、除菌シートやアルコールで拭き取ります。土の表面にカビがあるなら、その部分の土を取り除き、新しい土を補充しましょう。次に、鉢全体にカビが回っているようなら、植物を鉢から取り出して根を洗い、乾燥させた後に植え替える必要があります。その際、使用する土や鉢は清潔なものを選び、再発防止を心がけてください。作業後は必ず水やりを数日間控え、植物の様子を見守りましょう。急いで処理するよりも、丁寧な作業が結果的に早期回復につながります。
アルコールは有効か?
アルコールはカビ対策に有効な手段の一つです。特に、葉や茎に付着した白カビに対しては、エタノールスプレーを使用することで除去効果が期待できます。使い方は簡単で、カビが確認できる部分にスプレーし、数分おいてからティッシュや柔らかい布で優しく拭き取ります。ただし、濃度が高すぎるアルコールは植物にダメージを与えることもあるため、70%前後の濃度が推奨されます。また、使用後は植物が乾燥するまで日陰で管理し、様子を観察してください。アルコールは殺菌力が強い一方で、頻繁に使うと葉の油分が奪われるおそれもあります。必要な場面に絞って使うことが効果的です。
薬のおすすめ殺菌剤
カビの再発や進行を防ぐには、市販の殺菌剤を活用するのも効果的です。中でも「ベンレート水和剤」や「STサプロール乳剤」は、多肉植物にも使用可能で、広範囲のカビに対応できます。これらは希釈して使用するタイプで、葉や土にまんべんなく散布することでカビの発生源を抑える働きがあります。また、スプレータイプの「ベニカXネクストスプレー」などは手軽に使える上、病気と害虫の両方に対応しており初心者にも向いています。ただし、使用頻度や濃度には注意が必要です。植物にダメージを与えないよう、説明書をよく読み、適切な量を守って使用してください。


ベニカは使えるのか?
「ベニカ」シリーズは、多肉植物に使用可能な殺菌・殺虫剤として人気があります。特に「ベニカXファインスプレー」は、うどんこ病や灰色カビ病といったカビの予防に効果があるため、多肉植物の管理にも適しています。一方で、治療効果はなく予防目的が中心となるため、カビがすでに広がっている場合は別の薬剤と併用する必要があります。より強力な対応が必要なときは「ベニカXネクストスプレー」のような治療効果もある製品が適しています。ただし、使用回数が多すぎると植物に負担がかかるため、週1回を目安に使用し、様子を見ながら調整することが大切です。
多肉植物に白いカビが生えた時の対処法についてのまとめ
- 白いふわふわはカビ・カイガラムシ・ブルームのいずれかである
- カビは湿度と通気性の悪さが原因で発生する
- カイガラムシは白い粒状の害虫で、植物に害を与える
- ブルームは植物が出す天然の粉で無害である
- 白い粒が葉に点在する場合はカイガラムシの可能性が高い
- 白い粉が広範囲に広がり葉が変色するなら病気の可能性がある
- 白カビは植物の成長を阻害し、根腐れの原因になることもある
- 室内では白カビの胞子が飛び、アレルギーリスクがある
- 鉢にカビが出たら表面の土を除去し風通しを改善するべき
- 葉に白い粉やベタつきが出たら初期症状の可能性がある
- カビが見つかったらティッシュやアルコールで除去する
- カビが土の奥に広がっている場合は植え替えが必要
- 除去後は風通しと湿度管理で再発を防ぐことが重要
- アルコールスプレーは軽度の白カビ除去に有効である
- ベニカやベンレートなどの殺菌剤は予防・治療に役立つ




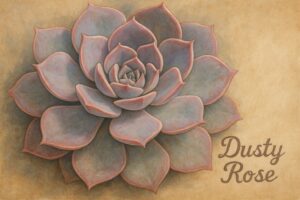


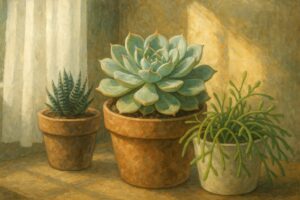


コメント